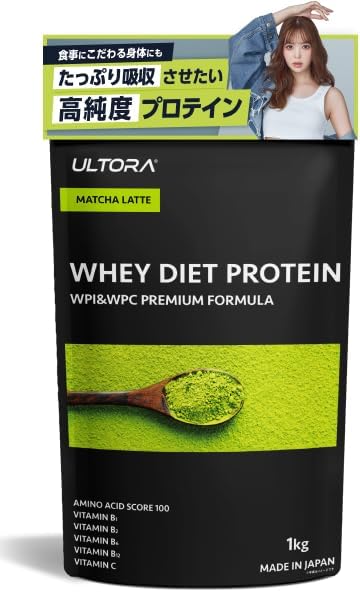たんぱく質ダイエットとは?正しいやり方とおすすめ食材・メニューまとめ

- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
- 美味しさ、安さ、手軽さ、安全性を追求した冷凍宅配弁当
- 【ハピマガ限定】初回2,000円OFFで購入可能
- 【総額5,000円OFF】2〜4回目も1,000円OFF!
監修者情報

板垣 奏穂
管理栄養士
管理栄養士と栄養教諭として働いた経験を活かし、食に関する記事の監修などを行う。
経営者支援事業などを展開する株式会社バシコミを経営するかたわら、プライベートでは20種類以上のアレルギーを持つ子どもの母でもあり、アレルギーや離乳食に関する相談の窓口としても活動している。
◼︎資格
管理栄養士
栄養教諭
みんなが知りたい!長く続けられる酵素ドリンク

たんぱく質ダイエットとは?

たんぱく質ダイエットとは、筋肉を維持しながら脂肪を効率的に落とすことを目的とした食事法です。
糖質制限や脂質制限のように特定の栄養を極端に減らすのではなく、1日に必要なたんぱく質量を体重に応じて計算します。
そのうえで、朝・昼・夜の食事に分けて、たんぱく質を摂るのが基本です。
具体的には、鶏むね肉・魚・卵・大豆製品などの高たんぱく食材を中心に取り入れ、糖質や脂質も適量を確保してバランスの取れた食事を心がけます。
こうすることで筋肉量を維持しつつ、基礎代謝の低下を防ぎながら体重を落とせるのが特徴です。
結果としてリバウンドしにくく、長期的に続けやすいダイエット方法として注目されています。
たんぱく質の役割と基礎知識
たんぱく質は筋肉や臓器、ホルモン、酵素などをつくる材料となる、生命維持に不可欠な栄養素です。
基礎代謝や免疫機能を支える働きもあり、不足すると疲労感や集中力の低下、体調不良につながることがあります。
またたんぱく質は髪や肌、爪などの美しさを守る働きもあり、見た目の印象にも直結する重要な栄養素です。
たんぱく質ダイエットはなぜ痩せる?
たんぱく質をしっかり摂ると、満腹感を得やすくなり自然と食欲をコントロールしやすくなります。
また、筋肉を維持したまま脂肪を減らすことができるため、基礎代謝の低下を防ぎ、リバウンドしにくい体づくりにつながります。
さらに「食事誘発性熱産生(DIT)」と呼ばれる仕組みにより、消化・吸収の過程でほかの栄養素よりも多くのエネルギーを消費するのも特徴です。
これらの働きが組み合わさることで、たんぱく質を意識した食事は効率的なダイエットにつながるのです。
糖質制限や脂質制限との違い
糖質制限はご飯やパン、麺類といった炭水化物を減らすことで血糖値の上昇を抑え、糖質依存度を下げる効果があります。
脂質制限は揚げ物や脂身の多い肉などを控え、摂取カロリーそのものを大きく減らすのに適した方法です。
これらに対して、たんぱく質ダイエットは筋肉を守りながら脂肪を効率よく減らせるのが最大の特徴です。
栄養を極端に制限する必要がないため体調を崩しにくく「食べながら痩せる」というバランスのよいダイエット法として注目されています。
たんぱく質ダイエットの正しいやり方

たんぱく質ダイエットは、単に「たんぱく質の摂取量を増やせば痩せる」というわけではなく、必要量の把握や食事全体のバランス、食べるタイミングなどを工夫することが成功のポイントです。
ここからは、具体的にどのようにたんぱく質ダイエットを実践すればよいのか順を追って解説します。
1日のたんぱく質必要量を体重から計算する
たんぱく質ダイエットを実践するには、まず自分に必要なたんぱく質量を把握することからはじめましょう。
たんぱく質の1日の摂取量目安としては、一般的な女性で体重1kgあたり1.2〜1.6g、運動習慣がある人や男性では1.5〜2.0g程度が適しています。
たとえば体重50kgの女性なら、1日あたり60〜80gのたんぱく質を摂るとよいということになります。
ただし、長期的に体重×1.6g以上を続けて摂取すると、腎機能に不安がある人では負担になる可能性もあります。
体重やライフスタイルに合わせて適量を意識することが、安全かつ効果的にたんぱく質ダイエットを進めるポイントです。
PFCバランスを整えて食事を組み立てる
たんぱく質を増やすことだけに意識を向けると、脂質や糖質が不足しがちになります。
健康的にダイエットを続けるためには、たんぱく質・脂質・炭水化物の三大栄養素のバランスを意識することが大切です。
目安となるのが P(たんぱく質):F(脂質):C(炭水化物)=3:2:5 という比率です。
たとえば、体重50kgの女性が1日1,800kcalを摂取する場合は以下のように計算します。
- たんぱく質(全体の30%)=1,800kcal × 0.3 ÷ 4kcal(1gあたりのカロリー)=約135g
- 脂質(全体の20%)=1,800kcal × 0.2 ÷ 9kcal(1gあたりのカロリー)=約40g
- 炭水化物(全体の50%)=1,800kcal × 0.5 ÷ 4kcal(1gあたりのカロリー)=約225g
このように、総摂取カロリーに各栄養素の割合をかけ、1gあたりのカロリーで割ると必要量を算出できます。
栄養素の比率を意識して食事を組み立てれば、筋肉を守りながら脂肪を効率よく燃焼できるでしょう。
さらに炭水化物を適量摂ることで、エネルギー不足による疲労や集中力低下を防ぎ、トレーニング効果の維持にもつながります。
朝・昼・夜で食べるタイミングを工夫する
たんぱく質は「いつ摂るか」によって体への影響が変わります。
朝食にたんぱく質をしっかり取り入れると、代謝が上がりやすく午前中のパフォーマンスも安定するでしょう。
運動を行う前後は、消化吸収の早いプロテインやささみ、豆腐などを活用してたんぱく質を摂取すると効率的に筋肉の回復を促せます。
夜は白身魚や豆腐ハンバーグなど消化にやさしい食材を選ぶと、胃に負担をかけず睡眠を妨げにくいのがメリットです。
続けやすい仕組みをつくる
ダイエットを長く続けるには「無理なく続けられる工夫」を取り入れることが大切です。
調理は、蒸す・焼く・電子レンジなどのシンプルな方法を中心にすれば、手間を減らしながら栄養をしっかり確保できます。
また、卵や納豆、ツナ缶などの高たんぱく食材を常備しておけば、忙しい日でもすぐに一品用意できて便利です。
さらに、調理の時間すら取りにくい人には宅食サービスを利用するのもおすすめです。
たとえば「nosh(ナッシュ)」なら、高たんぱく・低脂質のメニューがあらかじめ栄養設計されており、手軽に食べられるためダイエットを無理なく継続できます。
- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
たんぱく質ダイエットのメリット
たんぱく質ダイエットには、糖質制限や脂質制限などの方法にはない特徴的なメリットがあります。
最大の利点は、筋肉を守りながら脂肪を減らせることです。
筋肉量を維持することで基礎代謝の低下を防ぎ、リバウンドしにくい体質づくりに直結します。
加えて、たんぱく質は消化に時間がかかるため満腹感が持続しやすく、自然と食欲を抑えられるのもポイントです。
さらに、たんぱく質は美容面への効果も大きい栄養素です。
髪・肌・爪はすべてたんぱく質を材料として作られるため、十分に摂取することでツヤやハリが保たれ、見た目のコンディションも改善しやすくなります。
ダイエット中におすすめの高たんぱく食材

たんぱく質は肉・魚・卵・乳製品・豆類など、日常的に身近な食品からしっかり摂ることができます。
動物性と植物性の食品を組み合わせれば、アミノ酸のバランスが整い、より効率的に体づくりできるでしょう。
ここからは、ダイエット中でも取り入れやすい代表的な食材とその特徴をジャンルごとに紹介します。
肉類(鶏むね肉・牛赤身・豚ヒレ)
| 食材 | たんぱく質量(100gあたり) |
|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 23.3g |
| 牛もも赤身 | 21.3g |
| 豚ヒレ肉 | 22.2g |
肉類は、動物性たんぱく質を効率よく摂取できる代表的な食材です。必須アミノ酸がバランス良く含まれており、筋肉の維持や代謝アップに欠かせません。
脂質の少ない部位を選べば、ダイエット中でも安心して取り入れられます。
特に鶏むね肉は低脂質かつ高たんぱくで定番な食材です。
牛の赤身肉や豚ヒレも脂質が控えめで、筋肉づくりや体力維持に適しています。
調理法を工夫すれば、毎日の食事に飽きずに取り入れられます。
魚介類(サーモン・マグロ・エビ)
| 食材 | たんぱく質量(100gあたり) |
|---|---|
| サーモン | 20.1g |
| マグロ(赤身) | 26.4g |
| エビ | 19.8g |
魚介類は、高たんぱくであることに加え、オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)などの良質な脂質を摂れるのが大きな特徴です。
サーモンやマグロは、血流改善や代謝サポート、美容維持に役立つ栄養素が豊富で、筋肉の維持や疲労回復にも効果的です。
エビは低脂質・高たんぱくでカロリーを抑えやすく、夜ごはんや軽めにしたい食事にも取り入れやすいでしょう。
さらに、刺身・焼き魚・蒸し料理など調理法のバリエーションも多く、味に飽きにくいのも魅力です。
卵・乳製品(卵・ヨーグルト・カッテージチーズ)
| 食材 | たんぱく質量(100gあたり) |
|---|---|
| 卵(全卵) | 12.2g |
| ヨーグルト(無糖) | 3.6g |
| カッテージチーズ | 13.3g |
卵は「完全栄養食」と呼ばれるほどアミノ酸バランスが整っており、筋肉づくりにも美容にも効果的です。
ヨーグルトやカッテージチーズは消化にやさしく、カルシウムやビタミンも同時に摂れるのが魅力。
卵や乳製品は、朝食や間食に取り入れると続けやすく、食生活に自然に組み込みやすい食材です。
大豆・豆類(豆腐・納豆・枝豆・レンズ豆)
| 食材 | たんぱく質量(100gあたり) |
|---|---|
| 木綿豆腐 | 7.0g |
| 納豆 | 16.5g |
| 枝豆(ゆで) | 11.5g |
| レンズ豆(ゆで) | 11.2g |
大豆や豆類は、脂質が少なく植物性たんぱく質を効率よく摂れる食材です。
豆腐や納豆は日本人の食卓になじみ深く、腸内環境を整える食物繊維も同時に摂取できます。
枝豆は間食やおつまみにも向いており、レンズ豆はスープやサラダに加えるとヘルシーで満足感のある一品になります。
動物性たんぱく質を含む食材と組み合わせることで、栄養バランスがさらに良くなります。
ナッツ・シード類(アーモンド・チアシード)
| 食材 | たんぱく質量(100gあたり) |
|---|---|
| アーモンド | 19.6g |
| チアシード | 19.4g |
ナッツやシード類は、少量でたんぱく質と良質な脂質を摂れるのが特徴です。
アーモンドはビタミンEも豊富で、間食として取り入れると腹持ちが良くなります。
チアシードは水分を吸収して膨らむため、満腹感のサポートに役立ちます。
ただし、ナッツ・シード類は脂質が多いので、アーモンドなら1日20〜25粒(約25g)、チアシードなら大さじ2杯程度を目安にするとカロリー過多を防げます。
ダイエットに役立つ高たんぱくレシピ

高たんぱく食材は単品で食べるだけでなく、1日の食事にうまく取り入れることで効果を発揮します。
ここでは、朝・昼・夜それぞれのタイミングに適したメニューを紹介します。
手軽さと栄養バランスを意識したので、毎日の食事に取り入れやすい献立です。
朝ごはんメニュー
1日のはじまりの朝にたんぱく質をしっかり摂ることで、代謝がスムーズに働きやすくなり、午前中の集中力やパフォーマンス維持にもつながります。
特に朝は体内の栄養が枯渇しているため、良質なたんぱく質を補給することが大切です。
和食の朝食メニュー例
- 納豆
- 卵
- ご飯小盛
- 味噌汁
洋食の朝食メニュー例
- ギリシャヨーグルト
- ゆで卵
- 全粒パン
- 果物
発酵食品や炭水化物を組み合わせることで、腸内環境を整えながらエネルギーも補給できます。
さらに、和食は消化が良く胃にやさしいのが魅力で、洋食は時間がない朝でも手軽に栄養バランスを整えられるのがメリットです。
ランチメニュー
昼は活動量が増える時間帯なので、高たんぱくで腹持ちの良いメニューが最適です。
外出先でもコンビニを活用したり、作り置きのおかずをお弁当に入れたりすることで、安定してたんぱく質を確保できます。
コンビニで揃うランチメニュー例
- サラダチキン
- サラダ(卵やツナ入り)
- おにぎり1個
お弁当におすすめの作り置き
- 焼き鮭
- 豆腐入り鶏つくね
- ゆで卵の味玉
- ひじきと大豆の煮物
手軽さと栄養バランスを両立できるランチを意識することで、午後のエネルギー切れを防ぎ、仕事や運動のパフォーマンスも安定します。
夜ごはんメニュー
夜は体を休める準備をする時間帯なので、消化にやさしく睡眠を妨げないメニューを意識しましょう。
豆腐や白身魚を中心にした料理は胃に負担をかけにくく、ダイエット中でも安心して取り入れられます。
夜ごはんのメニュー例
- 白身魚の蒸し焼き+野菜添え
- 豆腐ハンバーグ
- 野菜スープ
- グリーンサラダ
- 雑穀ご飯(小盛)
野菜スープやサラダを組み合わせれば、ビタミンや食物繊維も補給でき、栄養バランスがさらに整います。
主食は消化に良いものを少量添えると、翌朝の体の回復やエネルギー補給にも役立ちます。
豆腐ハンバーグのレシピ(2〜3人分)
材料
- 鶏ひき肉 … 300g
- 木綿豆腐 … 150g
- 玉ねぎ … 1/2個
- 卵 … 1個
- 片栗粉 … 大さじ1
- 塩・こしょう … 各少々
- ごま油 … 小さじ1
- 酒 … 大さじ2
- 大根 … 7〜8cm(すりおろし)
- 大葉 … 3枚
- ポン酢 … 適量
作り方
- 豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをして10分ほど水切りする。玉ねぎは粗みじん切りにする。
- ボウルに鶏ひき肉、豆腐、玉ねぎ、卵、片栗粉、塩・こしょうを入れ、粘りが出るまで混ぜる。
- 2〜3等分に分けて成形し、フライパンにごま油を熱して両面に焼き色をつける。
- 酒を加えてふたをし、弱火で7〜8分蒸し焼きにする。
- 火が通ったら皿に盛り、大根おろしと千切りにした大葉をのせ、ポン酢をかけて完成。
たんぱく質ダイエットの注意点・デメリット

たんぱく質ダイエットは効果的なダイエット法ですが、正しい知識を持たずに実践すると健康を損なう可能性もあります。
ここでは、特に注意すべき5つのポイントについて確認しておきましょう。
摂りすぎによる腎臓や肝臓への負担
たんぱく質を必要以上に摂ると、代謝の過程で尿素やアンモニアといった老廃物が多く発生します。
これらを処理するために腎臓や肝臓がフル稼働することになり、余計な負担を与えてしまいます。
特に腎臓や肝臓に持病がある人や数値に不安がある人は、たんぱく質の過剰摂取が健康リスクにつながるため注意が必要です。
健康な人でも、体重や活動量に応じた摂取量の範囲を守ることが重要で、野菜や炭水化物を適度に組み合わせてバランスを取ることが安全に続けるコツです。
炭水化物不足で便秘や疲労感が出る
糖質を制限しすぎると、体のエネルギー源が不足し、疲労感や集中力の低下につながります。
さらに、炭水化物をほとんど摂らない食生活では食物繊維の摂取量も減りやすく、便秘や腸内環境の乱れを招きやすい点も問題です。
主食を完全に抜くのではなく、玄米や雑穀米、オートミールといった消化にやさしく栄養価の高い炭水化物を適度に取り入れることで、食事のバランスを保って無理なく続けられます。
水分と睡眠が不足すると効果が薄れる
たんぱく質を効率よく代謝するためには、十分な水分補給が欠かせません。水分が不足すると腎臓の働きに負担がかかり、老廃物の排出が滞って体調不良を招くおそれがあります。
さらに、睡眠が不足すると成長ホルモンの分泌が減少し、筋肉の合成や修復がスムーズに進まなくなる点は留意しましょう。
睡眠不足が続くと、たんぱく質ダイエットの効果が半減してしまうこともあります。
日中はこまめに水をとり、夜は6〜7時間以上の質の良い睡眠を確保することが、たんぱく質ダイエットの効果を最大限に引き出すための基本となります。
加工食品やプロテイン頼みの落とし穴
たんぱく質を手軽に補給できる加工肉やプロテイン食品は便利ですが、そればかりに頼るのはリスクがあります。
ハムやソーセージなどの加工肉は、添加物に加えて糖質や脂質を多く含み、知らないうちにカロリー過多になりやすいので注意しましょう。
また、市販のプロテインバーも一見ヘルシーに見えて、実際には砂糖や油脂が多く使われている製品が少なくありません。
栄養バランスを崩さないためには、肉・魚・卵・豆類といった自然な食材を中心に据え、加工食品や補助食品はあくまで「サポート役」として取り入れるのが安心です。
偏った食品選びによる栄養バランス崩れ
たんぱく質はどの食品から摂るかによって栄養バランスに差が出ます。
肉ばかりに偏ると脂質の過剰摂取や胃腸への負担につながり、長期的には体の不調を招く可能性があります。
一方で、大豆製品や豆類などの植物性たんぱく質を組み合わせれば、食物繊維やビタミン、ミネラルも同時に補えるため、栄養の偏りを防ぎやすくなります。
動物性と植物性の両方のたんぱく質食材を意識して取り入れることで、健康的に続けられるたんぱく質ダイエットにつながります。
栄養バランス崩れを防ぐなら宅食サービスが最も手軽
たんぱく質の摂取を意識していると、ハムやソーセージなどの加工食品や市販のプロテインバーに頼りがち。
しかし、これらは糖質や脂質が多く含まれている場合があり、気づかないうちにカロリーオーバーや栄養の偏りにつながることも少なくありません。
その点、宅食サービスなら管理栄養士監修の栄養バランスが整ったメニューを安心して食べられます。
調理の手間もなく、電子レンジで温めるだけで食事が完成するため、忙しい人でも続けやすいのがメリットです。
特に「nosh(ナッシュ)」は、高たんぱくかつ低糖質のメニューが揃い、和洋中と幅広い味付けで飽きにくいのが特徴です。
自分で食事を管理することが難しい人や、手軽に栄養バランスを整えたい人に特におすすめです。
- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
運動と組み合わせて効果を最大化

たんぱく質ダイエットの効果をより高めるには、食事だけでなく運動を組み合わせることが大切です。
有酸素運動と筋トレをバランスよく取り入れることで、脂肪燃焼と基礎代謝アップの両方を狙えます。
さらに、運動後のたんぱく質補給を意識することで、トレーニング効果を最大化できます。
有酸素運動で脂肪燃焼を促進する
ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、糖質と脂質をエネルギーとして消費し、20〜30分以上続けて行うと体脂肪の燃焼がより高まりやすくなります。
また、朝や食後の軽い運動は血糖値の安定にも役立ち、健康維持にも効果的です。
大切なのは、無理なく続けられるペースで行うことです。息が少し弾む程度を目安にすれば、長期的に習慣化しやすくなります。
筋トレで基礎代謝を上げる
筋肉量が増えると安静時の消費カロリーである基礎代謝が高まり、普段の日常生活の中でもエネルギー消費が大きくなります。
その結果、痩せやすく太りにくい体質づくりにつながります。
特にスクワットやデッドリフト、ベンチプレスなど大きな筋肉を使うトレーニングは効率的で、短時間でも効果を得やすいのが特徴です。
また、筋トレは基礎代謝を高めるだけでなく、リバウンドの防止にも効果的です。
たんぱく質を意識した食事と組み合わせて習慣化すれば、より安定した成果を得られるでしょう。
運動初心者でジムに通う場合は、基礎から丁寧に指導してくれる「チキンジム」の利用がおすすめです。
- チキンジム
- 株式会社クリア
運動後30分以内のたんぱく質補給が効果的
運動後の30分以内の時間は、筋肉が栄養を取り込みやすい「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間帯です。
このタイミングでたんぱく質を摂取すると、筋肉の回復と合成が効率よく進み、トレーニング効果を最大限に引き出せます。
特に消化が早いヨーグルトや豆腐、ゆで卵などは取り入れやすく、忙しい人でも無理なく続けられます。
さらに、より手軽に補給したい場合は「ウルトラホエイプロテイン」のような吸収の早いプロテインを飲むのもおすすめです。
たんぱく質ダイエットに関するよくある質問
ダイエット中にプロテインを飲んでも太らない?
プロテインは低脂質・低糖質で作られているものが多く、適量であれば太る心配はほとんどありません。ただし摂取量が多すぎると、総摂取カロリーが増えて体重増加の原因になります。
あくまで普段の食事で不足する分を補うサポート役として考えることが、プロテインを上手に活用するポイントです。
たんぱく質は食べすぎても大丈夫?
たんぱく質は体に必要な栄養素ですが、必要量を超えて摂ってもすべてが筋肉やエネルギーに使われるわけではありません。余った分は分解されて脂肪として蓄積される可能性があります。
さらに、代謝の過程で老廃物が増えるため、腎臓や肝臓に余計な負担を与えることもあります。健康的に取り入れるためには、体重や活動量に合わせて適量を守ることが重要です。
炭水化物を抜いてたんぱく質だけにしてもいい?
炭水化物は体にとって最も重要なエネルギー源のひとつであり、脳や筋肉の働きにも欠かせません。
完全に抜いてしまうと、エネルギー不足から疲労感や集中力の低下を招きます。
さらに炭水化物と合わせて摂取することが多い食物繊維不足によって便秘や腸内環境の悪化にもつながります。
そのため、炭水化物をゼロにするのではなく、玄米や雑穀米、さつまいもなど消化にやさしく栄養価の高い食材を適量取り入れることが大切です。
こうした工夫により、健康を損なわずにダイエットを長く続けられます。
無理なく続けられるたんぱく質ダイエットを目指そう

たんぱく質ダイエットは、筋肉を守りながら脂肪を減らし、リバウンドしにくい体をつくれる理想的な食事法です。
体重に合わせたたんぱく質の必要量を把握し、PFCバランスを意識して朝・昼・夜に分けて摂れば、無理なく実践できます。
肉や魚、卵、大豆製品などを組み合わせれば栄養も偏らず、美容や健康にも好影響があります。さらに運動や十分な休養を取り入れることで、引き締まった体と毎日の活力を手に入れられるでしょう。
無理なく続けられる工夫を取り入れ、自分に合ったペースで取り組んでいくのが長続きするコツです。