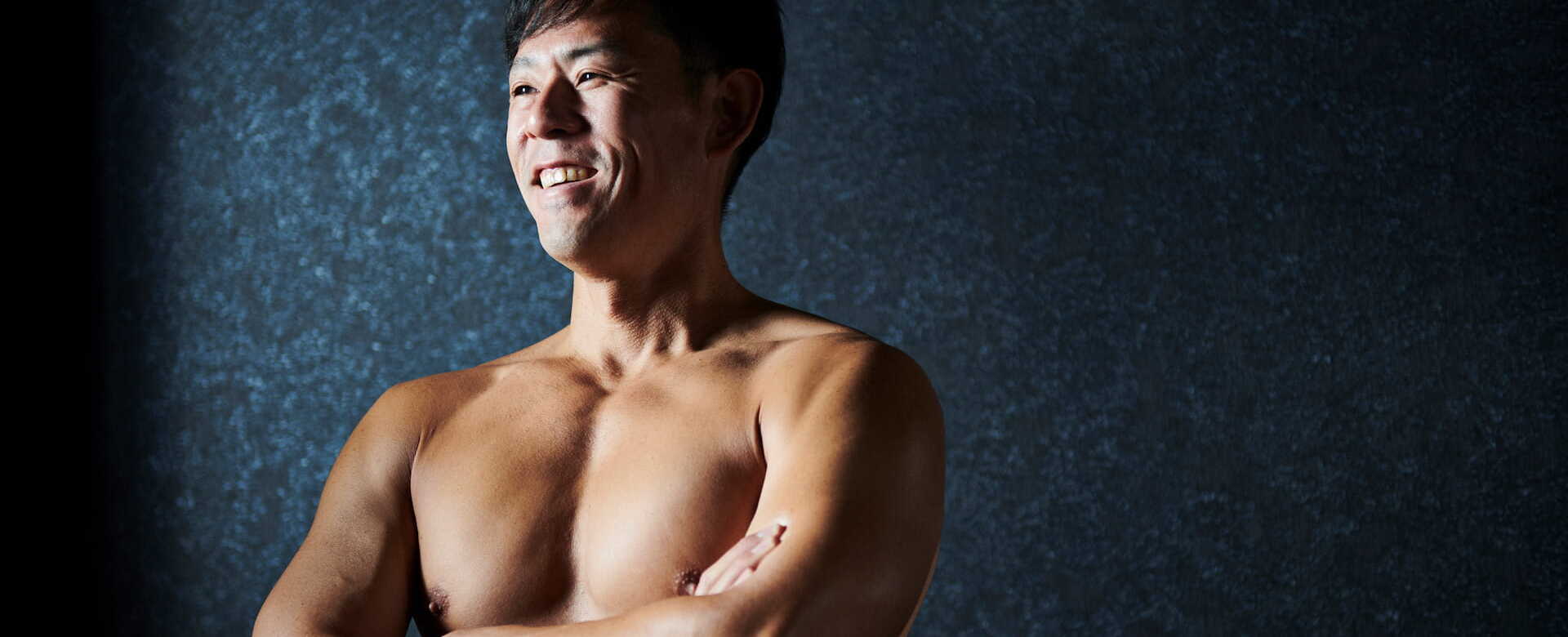寝違えたときに実践したいストレッチ3選!原因と予防策を知って再発防止へ

監修者情報

田中 咲百合
フィットネスインストラクター
フィットネスインストラクターとして30年以上の経験を持ち、ワタナベエンターテインメントのタレント育成学校や東京YMCA社会体育専門学校で指導を経て、今は人気講演講師として全国にて活動中(2024年度人気講師ランキング東日本7位、平均満足度92点)。
ヘルスケア商品の開発・エクササイズ監修、プロモーションにも多く携わり、年間売上5億円を達成した実績を持つ。
■資格
健康運動指導士
野菜ソムリエプロ
健康経営エキスパートアドバイザー
メンタルヘルスケア(2種・3種)
寝違えたときにしたい3つのストレッチ

田中 咲百合
寝違えたときの痛みを和らげるには、無理に動かすのではなく、適切なストレッチで筋肉をほぐすことが大切です。
寝違えによる痛みを和らげるには、硬くなった筋肉を無理なくほぐすストレッチが効果的です。ここでは、首、脇の下、肩甲骨まわりにアプローチする3つのストレッチを紹介します。
首のストレッチ
寝違えると首がこわばり、思うように動かせなくなることがあります。そのようなときは、無理のない範囲で首のストレッチを行い、筋肉をほぐしましょう。
まず、首を前後・左右にゆっくりと動かします。次に、痛みを感じない範囲で軽く左右に回旋させると、緊張が和らぎやすくなります。このとき、呼吸が止まらないよう注意し、深呼吸をしながらゆっくり行いましょう。
首のストレッチは、寝違えたときだけでなく、デスクワークなどで首に負担がかかる場面でも効果的です。スキマ時間に取り入れて、こまめにケアしましょう。
脇の下ストレッチ
脇の下の筋肉は首や肩とつながっており、ここをほぐすことで寝違えによる痛みの軽減が期待できます。
痛む側の腕を肩の高さまで上げ、肘を伸ばしたまま体の前にまっすぐ伸ばします。次に、反対の手で肘をつかみ、腕をゆっくりと反対側へ引っ張るように動かし、肩や脇の下の筋肉を伸ばしましょう。このとき、無理に力を入れず、心地よい伸びを感じる範囲で行うことが大切です。引っ張った状態で10秒間キープし、深呼吸をしながら筋肉を緩めます。
この動作を痛みが和らぐまで数回繰り返してください。ただし、強い痛みを感じる場合は無理をせず、ストレッチを中止しましょう。
肩甲骨ストレッチ
肩甲骨まわりをほぐすことで、首や肩への負担を軽減し、寝違えの痛みを和らげる効果が期待できます。
まず、壁に手をつき、肩を前に押し出すようにして肩甲骨まわりを伸ばします。次に、両手を背中で組み、肘を伸ばしながら肩甲骨を寄せる動作を行いましょう。それぞれの動作は10秒間キープし、無理のない範囲でゆっくりと繰り返します。
さらに、肩甲骨とつながる僧帽筋(そうぼうきん)の緊張をほぐすことも重要です。肩をすくめてからストンと落とす動作を数回繰り返すと、首の負担が軽減しやすくなりますよ。
そもそも「寝違え」とは?

寝違えとは、睡眠中の不自然な姿勢によって首や肩の筋肉に過度な負担がかかり、起床時に強い痛みや動きの制限が生じる症状のことを指します。
この痛みの原因として、首周辺の筋肉の軽度な肉離れや炎症、こむら返りなどさまざまなケースが考えられます。長時間、不自然な姿勢で寝ていると筋肉が部分的に血流不足(阻血状態)になり、起床時に急に首を動かすと、筋肉や靭帯が傷つき、痛みが悪化することも。
寝違えを防ぐためには、睡眠中の姿勢だけでなく、朝起きたときの動き方にも注意が必要です。
寝違えが起きる主な原因

寝違えは、単に「変な姿勢で寝たから起こる」というわけではなく、主に以下の4つの原因が関係しています。
- 睡眠中の不自然な姿勢
- 枕や寝具の影響
- 冷えによる筋肉の硬直
- 日常生活での習慣や負荷
睡眠中の姿勢だけでなく、枕や寝具の選び方、冷え、日常の姿勢や動作の癖も影響を与えることがあるのです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
睡眠中の不自然な姿勢
寝違えの主な原因は、睡眠中の首の姿勢です。長時間、首が不自然に曲がった状態が続くと、筋肉が血流不足になり、凝り固まってしまいます。特に、ソファや椅子で寝落ちすると、頭や首を十分に支えられず、不自然な姿勢が続いて首に大きな負担がかかります。
また、枕の高さが合っていない場合も、首が適切な位置に保たれず、筋肉が緊張しやすくなります。高さが低すぎると頭が沈み込み、逆に高すぎると首が持ち上がりすぎてしまい、どちらも寝違えのリスクを高めます。
さらに、寝返りが少ないと特定の部位に負荷が集中し、筋肉の緊張が強まることで痛みが生じることがあります。
枕や寝具の影響
寝違えは、睡眠中の姿勢だけでなく、枕やマットレスの影響によっても引き起こされることがあります。
特に、枕の硬さや弾力の違いが首への負担を左右します。枕が硬すぎると頭が安定せず首に力が入りやすくなり、逆に柔らかすぎると沈み込みすぎて正しい寝姿勢を維持しにくくなります。
マットレスの硬さも重要なポイントです。適度な硬さのマットレスは寝返りを促し、体圧を分散させる効果があります。一方、低反発マットレスのように柔らかすぎるものは体が沈み込み、寝返りが減ることで筋肉がこわばりやすくなります。
枕やマットレスが自分の体に合っていないと、首や肩に不要な負担がかかり、寝違えを繰り返す原因になります。朝起きたときに首や肩の違和感が続く場合は、一度寝具を見直してみましょう。
冷えによる筋肉の硬直
寝ている間に首や肩が冷えると、筋肉がこわばりやすくなり、寝違えを引き起こす原因になります。特に、エアコンをつけたまま寝たり、冬場に十分な暖房を使わずに寝る場合や、冬キャンプなどの屋外で防寒対策が不十分な状態だと、血流が悪化し、筋肉が緊張しやすくなります。
また、寒さで無意識に肩をすくめる姿勢が続くと、筋肉のこわばりが慢性化し、朝起きたときに首が動かしづらくなることがあります。
冷えによる寝違えを防ぐには、寝る前に筋肉を温め、血流を促進することが大切です。お風呂でしっかり体を温めた後にストレッチを行うと、筋肉がほぐれやすくなりますよ。
関連記事:お風呂上がりにできる簡単なストレッチについて解説した記事はこちら
日常生活での習慣や負荷
日常の姿勢や習慣が、首や肩の筋肉に負担をかけ、寝違えを引き起こす原因になることがあります。特に、長時間のデスクワークやスマホの操作は、首を前に突き出す姿勢を続けることになり、首や肩まわりの筋肉が慢性的に緊張しやすくなります。
さらに、猫背や前かがみの姿勢は、首に不自然な負荷をかけ、筋肉を過度に緊張させる原因となります。また、スポーツや重労働で首や肩の筋肉を酷使している場合も、疲労が抜けきらず、睡眠中に筋肉がこわばることで寝違えを引き起こしやすくなります。
こうした負担を軽減するためには、日頃からストレッチやマッサージで首や肩の緊張をほぐすことが重要です。ケアを怠ると筋肉のこわばりが慢性化し、寝違えを繰り返すリスクが高まります。
寝違えないための予防策3選

寝違えを防ぐには、日頃から首や肩の筋肉に負担をかけない習慣を身につけることが大切です。ここでは、以下の3つの予防策を紹介します。
- お風呂上がりや就寝前にストレッチと体の温めを行う
- 適切な枕と寝具を選択する
- 正しい姿勢に保持する
これらを実践することで、筋肉の緊張を和らげ、寝違えのリスクを減らすことができます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
お風呂上がりや就寝前にストレッチと体の温めを行う
寝違えを予防するには、寝る前にストレッチを行い、筋肉を温めて柔軟性を高めることが大切です。特に、首・肩・背中をしっかりほぐすストレッチを意識して行いましょう。
例えば、背中で指を組み、腕を遠くに伸ばして肩甲骨を引き寄せるストレッチは、肩まわりの可動域を広げ、筋肉の緊張をほぐすのに効果的です。また、寝る前にホットパックや蒸しタオルで首や肩を温めると、血流が促進され、筋肉がよりリラックスしやすくなります。ストレッチや首や肩を温めることで、寝違え予防だけでなく、入眠をスムーズにして睡眠の質を向上させる効果も期待できます。
また、肩甲骨まわりの動きをスムーズにする「肩甲骨はがし」も、冷えの改善や寝違え予防に効果的です。詳しいやり方については、以下の記事をご覧ください。
適切な枕と寝具を選択する
自分の体に合った枕やマットレスを選ぶことも、寝違えの予防に重要です。枕は、頭が反りすぎたり、沈み込みすぎたりしない適切な高さのものを選びましょう。横向きで寝たときに背骨がまっすぐになる高さが理想的です。枕の高さは体型や寝姿勢によって異なるため、一度寝具専門店などで測定してもらうと、自分に合ったものを選びやすくなりますよ。
マットレスも、寝返りを自然に打ちやすい硬めのものを選ぶのがおすすめです。低反発マットレスのように柔らかすぎるものは体が沈み込み、首や肩に負担をかけやすいため避けたほうがよいでしょう。
正しい姿勢を保持する
普段から正しい姿勢を意識することが、寝違えの予防につながります。特に、猫背の方は肩を引いて胸を開くことを意識し、背筋を自然に伸ばす姿勢を心がけましょう。
デスクワークのときは、あごを軽く引き、背筋を伸ばして座ることが大切です。パソコンを使う際は、画面の高さを目線と同じ位置に調整し、無理な前傾姿勢を防ぎましょう。また、長時間同じ姿勢でいると筋肉がこわばって首や肩に負担がかかるため、1時間に1回程度、軽くストレッチをするなどして体を動かすのがおすすめです。
スマートフォンを使うときも、下を向き続けると首に負担がかかるため、目線の高さを意識しながら使うようにしましょう。
寝違えたときのストレッチに関わるよくある質問

ストレッチを行う際の注意点は?
ストレッチを行う際は、無理をせず、痛みを感じたらすぐに中断することが大切です。無理に伸ばすと、筋肉や靭帯を傷める可能性があります。
また、ストレッチ中の呼吸も重要なポイントです。深呼吸をしながら、ゆっくりとした動作で行うことで、筋肉がよりリラックスしやすくなります。反動をつけず、心地よい範囲でじっくり伸ばしましょう。
寝違えによる強い痛みや腫れがある場合は、ストレッチを避け、まずは冷却を優先してください。炎症が落ち着いてから、無理のない範囲でストレッチを再開しましょう。
ストレッチは適度な負荷で継続することが重要です。毎日の習慣にすることで、首や肩の柔軟性を高め、寝違えの予防にもつながります。
ストレッチ以外の対処法はある?
寝違えてストレッチできないほど痛むときは、無理に動かさず安静にすることが最優先です。あわせて、アイシング(冷却)で炎症を抑え、患部に負担をかけないようにしましょう。
また、痛みが長引いたり、強い違和感が続いたりする場合は、整形外科を受診しましょう。市販の痛み止めを服用する場合は、用法・用量を守り、持病や薬の飲み合わせに不安がある場合は医師や薬剤師に相談してください。
寝違えを防ぐために、ストレッチと生活習慣の見直しを!

寝違えは、睡眠中の不自然な姿勢や合わない寝具、冷えなどが原因で首や肩の筋肉に負担がかかることで発生します。痛みを和らげるには、無理のない範囲でストレッチを行い、筋肉をほぐすことが大切です。
また、寝違えを繰り返さないためには、枕やマットレスを見直し、寝る前にストレッチや体を温める習慣を取り入れることも効果的です。毎日のちょっとした工夫で、首や肩への負担を減らし、快適な朝を迎えましょう。