たんぱく質の摂りすぎサインと症状|どれくらいが目安?改善法・食事のポイントを徹底解説

- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
- 美味しさ、安さ、手軽さ、安全性を追求した冷凍宅配弁当
- 【ハピマガ限定】初回2,000円OFFで購入可能
- 【総額5,000円OFF】2〜4回目も1,000円OFF!
監修者情報

板垣 奏穂
管理栄養士
管理栄養士と栄養教諭として働いた経験を活かし、食に関する記事の監修などを行う。
経営者支援事業などを展開する株式会社バシコミを経営するかたわら、プライベートでは20種類以上のアレルギーを持つ子どもの母でもあり、アレルギーや離乳食に関する相談の窓口としても活動している。
◼︎資格
管理栄養士
栄養教諭
みんなが知りたい!本当に美味しい宅食比較
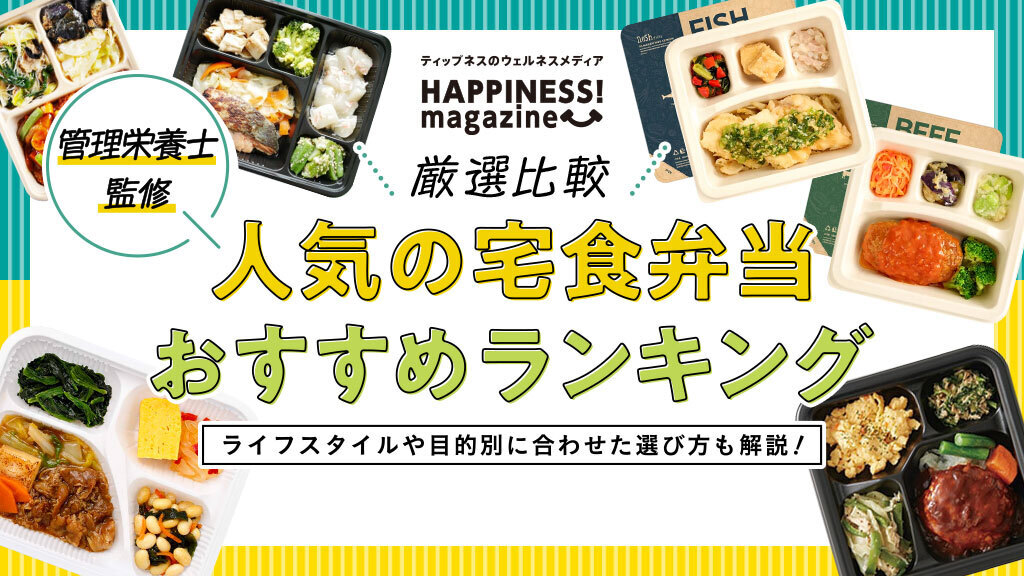
たんぱく質とは?基礎知識と体での役割

たんぱく質は、炭水化物・脂質と並ぶ三大栄養素のひとつで、体を形づくる基盤となる成分です。
筋肉や皮膚、髪の毛、爪など外見に関わる組織の材料となるほか、ホルモンや酵素、免疫細胞の生成にも欠かせません。
健康だけでなく美容面にも直結する、まさに体の土台と言える栄養素です。
また、通常は糖質や脂質がエネルギー源として優先的に使われますが、不足したときにはたんぱく質が代わりにエネルギー源となります。
たんぱく質の必要量を摂取することは、代謝を安定させ、日常生活を活発に送るためのカギとなります。
さらに、体内のたんぱく質は常に分解と合成を繰り返し、新しい細胞や組織を作り出しています。
このため、成長期の子どもや筋トレをしている人はもちろん、加齢により筋肉量が減少しやすい世代でも意識して、たんぱく質を摂ることが大切です。
たんぱく質を摂りすぎると起きるサイン・症状
たんぱく質は私たちの体にとって大切な栄養素のひとつです。
しかし、大切な栄養でも摂りすぎは禁物。
本章では、たんぱく質の摂りすぎで起こる体のサインについて解説します。
- 太る・体重が増える
- おならが臭くなる・便通異常
- 倦怠感・疲れやすさ・食欲不振
- むくみやすくなる
- 尿が濃くなる・腎臓に負担がかかる
- 髪の毛・肌への悪影響
たんぱく質の摂りすぎかも?と思う方はチェックしてみてくださいね。
太る・体重が増える
たんぱく質を摂りすぎてしまうとカロリーオーバーとなり、体重の増加につながります。
たんぱく質は糖質よりも積極的に摂りたい栄養素ですが、たんぱく質を多く含む肉や魚、大豆や乳製品には脂質も含まれています。
たんぱく質や炭水化物は1g当たり4kcalなのに対して、脂質は1g当たり9kcalと高カロリーなので、たんぱく質を積極的に摂ることで脂質も摂りすぎれば、カロリーオーバーにつながるでしょう。
カロリーの多い食事は、体重が増える原因になります。
おならが臭くなる・便通異常
たんぱく質を摂りすぎたサインとしてあらわれやすいのが、おならの悪臭や便通の乱れです。
特に肉や魚などの動物性たんぱく質を過剰に摂ると、腸内で分解されなかったたんぱく質が悪玉菌のエサとなり、腸内環境が悪化しやすくなります。
その結果として、おならがいつもより臭く感じたり、便秘や下痢といった症状が起こることがあります。
これを防ぐには、たんぱく質だけでなく食物繊維もしっかり摂ることが大切です。
食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内のバランスを整えてくれるうえ、便のかさを増やしてスムーズな排便を促してくれます。
食物繊維は、野菜やきのこ類に豊富に含まれています。
炒めものやスープに入れれば、カサが減って食べやすくなるでしょう。
また、食物繊維が豊富に含まれたサプリやドリンクで足りない食物繊維を補ってあげるのもおすすめです。
倦怠感・疲れやすさ・食欲不振
たんぱく質を摂りすぎると、だるさや疲れやすさ、食欲がわかないといった体の不調があらわれることがあります。
これらの症状の背景にあるのが、肝臓への負担です。
体内で余分なたんぱく質は窒素を含む物質に分解され、最終的にアンモニアへと変化します。
アンモニアは強い毒性をもつため、肝臓が尿素へと変換し、無害化したうえで体外へ排出する仕組みです。
しかし、たんぱく質を過剰に摂取するとアンモニアの処理が追いつかず、肝臓が疲弊してしまいます。
肝臓が疲れると、全身のだるさや疲労感、さらには食欲不振などの不調につながります。
単なる栄養の摂りすぎと軽く見ず、たんぱく質の摂取量が適正かどうか、一度見直してみることが大切です。
むくみやすくなる
むくみやすくなることも、たんぱく質の摂りすぎサインのひとつです。
たんぱく質を摂りすぎると、体の中で余ったたんぱく質(老廃物)を尿として体外に排出するため腎臓に負担がかかり、腎機能の悪化を引き起こす場合があります。
腎機能が悪化してしまうと、体内の老廃物を排出する働きが低下するため、むくみにつながるのです。
むくみやすくなったと感じたときは、たんぱく質の摂取量も見直してみましょう。
尿が濃くなる・腎臓に負担がかかる
たんぱく質を摂りすぎると、尿が濃くなる・泡立つといった変化が起こることがあります。
これは、腎臓が体内の老廃物や窒素を処理する負担が大きくなっているサインかもしれません。
たんぱく質を代謝する際には、アンモニアなどの有害物質が発生します。
これを無毒な尿素へと変換し、尿として排出するのが腎臓の役割です。
しかし過剰な摂取が続くと、腎臓は処理しきれずに疲弊し、体外への排出機能が低下してしまいます。
こうした状態が続くと、尿路に結晶(結石)が形成されやすくなり、尿路結石のリスクが高まるので注意しましょう。
特に動物性たんぱく質を多く摂っている人は、尿中のシュウ酸や尿酸の濃度が上がり、結石ができやすい環境になるとされています。
予防のためには、動物性ばかりに偏らず、豆類や穀物などの植物性たんぱく質も意識して摂取することが大切です。
あわせて、1日を通してこまめに水分を摂る習慣も腎臓を守るサポートになります。
髪の毛・肌への悪影響
たんぱく質は髪や肌の材料になるため、美容のために積極的に摂っている人も多いかもしれません。
しかしたんぱく質を摂りすぎると美容トラブルの原因になることがあります。
高たんぱくな食事ばかりに偏ると、ビタミンやミネラルが不足しやすくなります。
特にビタミンB群や亜鉛が足りないと、髪の成長や肌の生まれ変わりに影響が出て、抜け毛や髪のパサつき、肌荒れにつながるおそれがあります。
また、コラーゲンの生成に必要なビタミンCが不足すると、肌のハリや潤いが失われやすくなります。
たんぱく質だけに偏った食事は、美容のためのつもりがかえって逆効果になることもあるのです。
美容を意識するなら、野菜や果物、海藻類なども一緒に摂って、栄養バランスを整えることが大切です。
「たんぱく質を多く摂ればきれいになる」と思い込まず、適量を守って取り入れましょう。
現代人にたんぱく質の摂りすぎが増えている理由
たんぱく質は、健康や美容、ダイエットに欠かせない栄養素であり、積極的に摂る人が増えています。
筋トレブームや高たんぱく志向の広がりもあり「たんぱく質を多く摂るほどいい」と考える風潮が強まってきました。
加えて、プロテインドリンクやたんぱく質入りのお菓子などが手軽に手に入るようになり、気づかないうちに摂取量が上限を超えてしまうケースも増えています。
糖質を控える食事法が流行したことで、たんぱく質ばかりに偏った食生活になっている人も少なくありません。
栄養バランスを見直したいときは、たんぱく質・脂質・炭水化物のPFCバランスがしっかり管理された宅食サービスを取り入れるのもひとつの手です。
自炊では難しい栄養のコントロールも、手軽に続けやすくなります。
- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
たんぱく質の適切な摂取量はどれくらい?

たんぱく質の摂りすぎを防ぐためには、適切な量を把握することが大切です。
また、たんぱく質の不足は肌荒れや筋力の低下につながるため、過不足の少ない食生活を心がけましょう。
ここでは、たんぱく質摂取量の目安と摂取量の上限値について説明するので、参考にしてくださいね。
性別や年齢によって異なりますので、自分にとってどのくらいのたんぱく質が適量か知っておきましょう!
1日の摂取量の目安
厚生労働省が発行している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日のたんぱく質摂取量の目安は以下の通りです。
成人男性(18~64歳):65g
成人男性(65歳以上):60g
成人女性(年齢問わず):50g
たとえば鶏むね肉100gのたんぱく質量は21gなので、成人女性の場合250gの鶏むね肉で1日のたんぱく質摂取量の目安に達します。
また、1食でたんぱく質を一気に摂ると内臓に負担がかかるだけでなく、吸収しきれなくなってしまうため、1日の食事を通してバランスよく摂取するのがおすすめです。
摂取量の上限値と注意点
たんぱく質は健康や美容に欠かせない栄養素ですが、摂りすぎには注意が必要です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より、1日のたんぱく質摂取量の上限は「摂取エネルギー量の20%」とされています。
1日の摂取エネルギーは性別、年齢、運動の多さによって異なります。
たとえば、30代女性の1日あたりのエネルギー摂取量の目安は1,750〜2,350kcalとされており、たんぱく質で換算すると約87.5〜117.4gが上限となります。
この量を大きく超えると、肝臓や腎臓に負担がかかったり、腸内環境の悪化や疲労感、むくみに尿路結石といったさまざまな不調につながるリスクがあるため注意が必要です。
たんぱく質は「多ければ多いほどいい」という思い込みではなく、自分に合った摂取量を意識し、適量を守ることを心がけましょう。
摂りすぎを防ぐ!上手なたんぱく質の摂取方法
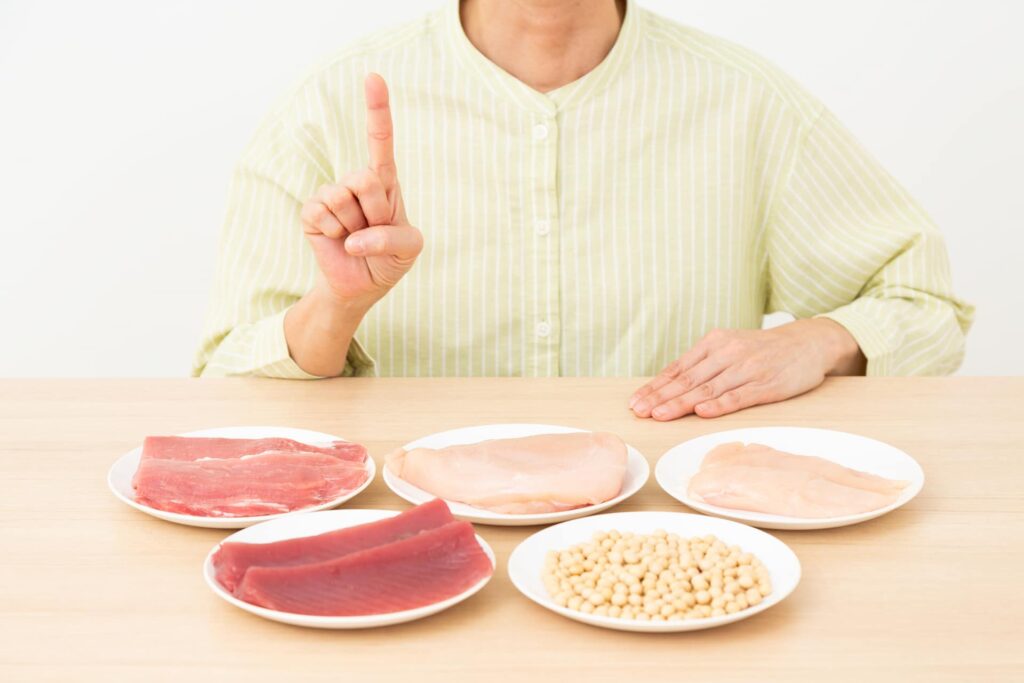
たんぱく質の摂りすぎも摂らなすぎも体に良くないとはいえ、適切な量を上手に摂取するのは難しく感じますよね。
本章では、日々の中で上手にたんぱく質を摂取するコツを解説します。
- たんぱく質が多い食べものを食事に取り入れる
- たんぱく質は“いつ・どう摂るか”も大切
- 主食・副菜と組み合わせるポイント
- プロテインは飲みすぎに注意して活用
- 宅食サービスで栄養バランスを整える
- 栄養補助食品を活用する
ぜひ参考にして、適切にたんぱく質を摂取しましょう!
たんぱく質が多い食べものを食事に取り入れる

たんぱく質摂取量の上限値に気をつける必要はありますが、効率的にたんぱく質を摂るためには、普段の食事に高たんぱくな食材を取り入れることが重要です。
普段の食事で取り入れやすいたんぱく質を多く含む食材には以下のようなものがあります。
- 卵
- 肉(鶏むね肉や赤身肉)
- 魚
- 納豆
- 豆腐
たとえば、朝に納豆や卵、昼に鶏肉、夜に魚や豆腐を取り入れることで、1日を通じて無理なくたんぱく質を分散して摂取できます。
たんぱく質が多く含まれる食材をさらに知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
おすすめ高たんぱくレシピ3選
以下では、高たんぱくなおすすめレシピを3つ紹介します。毎日の食事にぜひ活用してみてください!
鶏むね肉のピリ辛ねぎソース和え
<材料(2人分)>
鶏むね肉:250g
酒:大さじ1
みりん:大さじ1
(ピリ辛ねぎソース)
長ねぎ(みじん切り):30g
ポン酢:大さじ2
ごま油:大さじ1
豆板醤:小さじ1/2
すりおろししょうが:小さじ1
白ごま(お好みで):適量
<作り方>
- 鶏むね肉は皮を取り除き、フォークで数か所穴を開けて一口大に切り分ける。
- 耐熱皿に鶏むね肉を並べ、酒とみりんを回しかけて絡める。10分ほど置いて下味をつける。
- ラップをふんわりとかけ、電子レンジ600Wで2分加熱する。一度取り出して裏返し、さらに600Wで2分加熱する。火が通っていない場合は追加で加熱する。
- 小さなボウルに長ねぎ、ポン酢、ごま油、豆板醤、すりおろししょうがを入れて混ぜ合わせ、ピリ辛ねぎソースを作る。お好みで白ごまを加える。
- 加熱した鶏むね肉を皿に盛りつけ、ソースをたっぷりとかければ完成。お好みでパクチーや糸唐辛子をトッピングしても。
鶏むね肉の南蛮風ソテー(2人分)
<材料(2人分)>
鶏むね肉:1枚(約350g)
塩こしょう:適量
小麦粉:適量
卵:1個
サラダ油:適量
(A)
酢:大さじ2
しょうゆ:大さじ1
はちみつ:大さじ1
すりおろしにんにく:小さじ1
(ヨーグルトタルタルソース)
プレーンヨーグルト:大さじ2
玉ねぎ(みじん切り):15g
ピクルス(みじん切り):10g
塩こしょう:適量
<作り方>
- 酢、しょうゆ、はちみつ、すりおろしにんにくを混ぜ合わせて甘酢ソースを作る。
- 玉ねぎとピクルスをみじん切りにし、ヨーグルトと塩こしょうを混ぜてヨーグルトタルタルソースを作る。
- 鶏むね肉をそぎ切りにし、塩こしょうで下味をつける。全体に小麦粉をまぶしておく。
- 卵を割りほぐし、3の鶏むね肉をくぐらせる。
- フライパンにサラダ油を熱し、卵をまとわせた鶏むね肉を中火で両面こんがり焼く。
- 焼き上がった鶏むね肉に(A)を加え、全体に絡めながら1~2分ほど加熱する。
- 盛り付けた鶏むね肉にヨーグルトタルタルソースをかけて完成。
ブロッコリーとゆで卵のごまヨーグルトサラダ
<材料(2人分)>
ブロッコリー:120g(半株)
卵:2個
塩:小さじ2(茹で用)
かつお節:2g
(ごまヨーグルトドレッシング)
すりごま:大さじ1
プレーンヨーグルト:大さじ2
しょうゆ:小さじ1
はちみつ:小さじ1
オリーブオイル:小さじ1
<作り方>
- ボウルにすりごま、ヨーグルト、しょうゆ、はちみつ、オリーブオイルを入れて混ぜ、ドレッシングを作る。
- 鍋に卵を入れて固ゆで卵を作る(沸騰後10~12分)。茹で上がったら冷水に取って殻をむいておく。
- 鍋に水(1リットル)を沸かし、塩(小さじ2)を加える。ブロッコリーをよく洗い、小房に分け、茎は皮をむいて薄切りにする。すべてを1~2分茹でた後、ざるに上げて粗熱を取り、キッチンペーパーで水気を拭き取る。
- ゆで卵をボウルに入れ、フォークで粗くつぶす。
- ボウルにブロッコリー、つぶしたゆで卵、ドレッシング、かつお節を加え、全体をよく和える。
- 器に盛り付けて完成。追加でかつお節をトッピングしてもOK。
また、料理に時間をかけられない方は、バランスの良い食事が手軽に楽しめる宅食弁当を活用してみましょう。
たんぱく質は“いつ・どう摂るか”も大切
たんぱく質をしっかり摂ることは大切ですが、摂取の「タイミング」や「組み合わせ方」にも気を配ることで、より効果的に体づくりや健康維持につなげられます。
たとえば、1日分のたんぱく質を朝昼晩に分けて摂ることで、体への吸収効率が高まり、内臓の負担も軽減されます。1食あたり20g前後を目安に、バランスよく分散させるのが理想的です。
また、卵や納豆、肉、魚など異なるたんぱく源を使い分けることで、栄養の偏りを防ぐことができます。
就寝前に消化の負担がかかる高たんぱくな食事を避けることも、快適な睡眠や翌日の体調管理につながります。朝や昼のうちにしっかり摂っておく意識も大切です。
たんぱく質は、量だけでなく「どう摂るか」まで考えることで、健康へのメリットをより引き出せます。
主食・副菜と組み合わせるポイント
たんぱく質は、それ単体で摂るのではなく、主食や副菜と組み合わせて食べることで、体への吸収効率や健康へのメリットが高まります。
それぞれの役割を理解し、バランスの良い食事を心がけましょう。
主食の役割(糖質エネルギー源)
ご飯やパンなどに含まれる糖質は、筋肉や脳の主要なエネルギー源です。
たんぱく質と一緒に摂ることで、筋肉合成を助け、日常のパフォーマンス維持にもつながります。
一方で、糖質が不足すると、たんぱく質がエネルギーとして使われてしまい、たんぱく質本来の「体づくり」という役割を果たせなくなる恐れがあります。
副菜の役割(ビタミン・食物繊維)
野菜やきのこ類に豊富なビタミン・ミネラルは、たんぱく質の代謝をサポートする重要な栄養素です。
さらに、食物繊維が腸内環境を整えてくれるため、おならや便通のトラブル予防にも効果的です。
副菜を添えることで見た目にも満足感が増し、過剰な食べすぎを防ぐ効果も期待できます。
プロテインは飲みすぎに注意して活用

生活リズムや仕事などの都合で、食事からたんぱく質を摂ることが難しい場合は、プロテインもおすすめです。朝や間食、寝る前など自分の好きなタイミングで活用しましょう。飲むだけで足りないたんぱく質を補給できるため、忙しい朝や夜でも手軽に栄養補給ができます。
また、プロテインはダイエットにもおすすめです。ダイエットを成功させるには基礎代謝を上げるための筋肉が欠かせません。たんぱく質は筋肉づくりに関わる栄養素のため、プロテインを飲むことはダイエットに必要なたんぱく質の補給につながるでしょう。
ただし、食事量をそのままにプロテインを飲みすぎるとカロリーオーバーにつながり、太る原因となります。朝食をプロテインにするなど、置き換えて無理なく取り入れましょう。
宅食サービスで栄養バランスを整える
忙しくて自炊が難しい人や、毎日の献立を考えるのが負担に感じる人には、宅食サービスの活用がおすすめです。
最近では、たんぱく質・脂質・炭水化物の「PFCバランス」が計算されたメニューが多く、栄養の過不足を防ぎながら効率的に食事管理ができます。
なかでも、冷凍で届いて電子レンジで温めるだけの「nosh(ナッシュ)」は、糖質や塩分にも配慮されており、ダイエット中や体づくりを意識している人にもぴったりです。
自炊に自信がない人や、コンビニに頼りがちな生活から脱却したい人は、こうしたサービスをうまく取り入れることで、無理なく健康的な食習慣を続けることができます。
- ナッシュ(nosh)
- ナッシュ株式会社
栄養補助食品を活用する

肉や魚が食べられなかったり、プロテインの味が苦手だったりと、なかなかたんぱく質を摂取できない方は、コンビニやスーパーに売っているプロテインバーなどの栄養補助食品を活用するのもおすすめです。
最近は食べやすい味のものや甘いものも多く、お菓子などの代わりとしても良いでしょう。
ただし、糖質も多く含まれているので食べすぎには注意してください。
たんぱく質の摂りすぎサインにはご注意を!

私たちの体にたんぱく質は必要不可欠ですが、摂りすぎには注意が必要です。
以下の症状に心当たりがある場合は、たんぱく質の摂取量を見直してみましょう。
- 体重が増える
- おならが臭くなる
- 体に不調があらわれる
- むくみやすくなる
また、本記事ではたんぱく質の摂取目安量や摂取上限量、たんぱく質を上手に摂るコツについても解説しました。
自分の年齢や生活をもとに、適切なたんぱく質量を把握することが大切です。たんぱく質の摂りすぎサインに注意して、上手に摂取していきましょう!


















