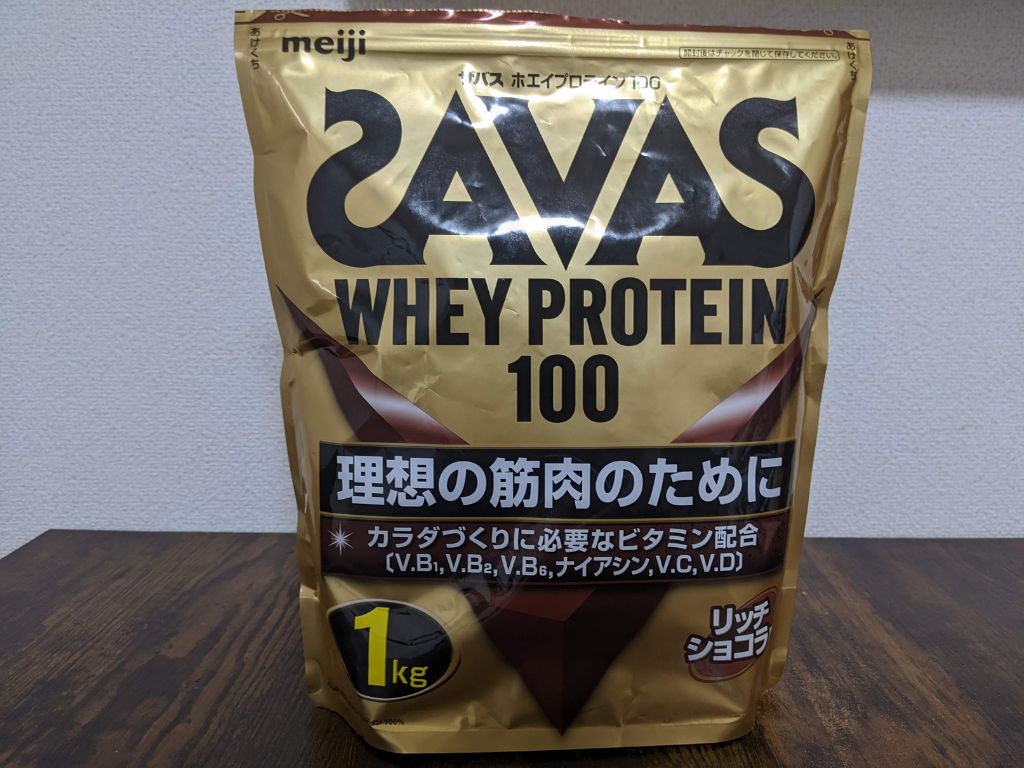食後に眠くなる対策は?眠気がひどい原因は血糖値スパイクが関係

監修者情報

湯浅 道子
美容家
大手エステティックサロンで8年勤務しトータル美容を学ぶ。コスメコンシェルジュを取得し、雑誌「Ray」のベスコス選定員の経験も。
さまざまなメディアで、思春期世代から更年期世代までの幅広い美容情報の発信、監修をおこなう。
◼︎資格
日本化粧品検定1級・2級
コスメコンシェルジュ特級
コスメ薬事法管理者
薬機法管理者
景表法検定1級
みんなが知りたい!本当に着心地がいいリカバリーウェア

そもそも食後の眠気の原因とは?血糖値スパイクとの関係も解説


湯浅 道子
食後の眠気は、血糖値スパイクや疲労の蓄積、消化活動、睡眠不足などが原因です。特に血糖値の急上昇と急降下が眠気を強める原因のひとつとされています。
食後に強い眠気を感じるのは、単なる睡眠不足だけが原因とは限りません。
「血糖値スパイク」や疲労の蓄積、さらには消化によるエネルギー消耗など、さまざまな要因が関わっています。
ここでは、食後の眠気の主な4つの原因についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①血糖値スパイク(血糖値の急上昇)
食後の眠気の代表的な原因が「血糖値スパイク」です。血糖値スパイクとは、食事のあとに血糖値が急激に上がり、その後急激に下がる現象を指します。
通常、血糖値はゆるやかに変動するものですが、特に白米・パン・麺類などの精製された炭水化物を多く摂ると、血糖値の急上昇・急降下が起きやすくなります。
血糖値が急上昇すると、体は血糖値を抑えるために大量のインスリンを分泌します。
すると今度は血糖値が下がりすぎてしまい、一時的な低血糖状態に。
これが、だるさや眠気、集中力の低下といった症状を引き起こします。
血糖値スパイクは糖尿病リスクの上昇にもつながるため、眠気対策だけでなく健康管理の面でも無視できません。
血糖値を安定させることが、午後のパフォーマンス維持にも役立ちます。
②疲労の蓄積
慢性的な疲れは、食後の強い眠気を引き起こす原因のひとつです。
特に睡眠不足が続いていると、自律神経のバランスが乱れ、血糖値のコントロールが難しくなり、眠気がより強くなる傾向があります。
さらに疲労が長期間にわたって蓄積している場合、消化機能や神経系の働きにも支障をきたし、体全体の回復力が低下。
疲れやすい状態が続き、昼食後に強い眠気を感じやすくなります。
最近の睡眠時間や睡眠の質に不安がある方は、まず生活リズムを見直すことが重要です。
眠気を一時的にごまかそうと栄養ドリンクに頼る人もいますが、根本的な解決にはなりません。
本質的な改善には、質の高い休息とバランスの取れた食生活が不可欠です。
忙しい中でも、意識的に睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
③消化活動
食後に眠気を感じるのは、消化にともなう体内の反応も一因です。
食べ物を分解・吸収するためには多くのエネルギーが必要で、その際、血液が消化器官に集中します。
その影響で脳への血流が一時的に減少し、思考が鈍くなったり、眠気を催しやすくなります。
特に、脂質が多い食事や、消化に時間がかかる揚げ物・こってりした料理などを食べた場合、消化にかかる負担が大きくなり、眠気が強まる傾向があります。
「お昼にボリュームのある食事をとると、午後はいつも眠くなる」と感じている方は、食事内容による消化負担が関係しているでしょう。
④そもそもの睡眠不足
睡眠不足が続くと自律神経が乱れ、血糖値のコントロールが難しくなります。
その結果、食後の眠気がさらに強く表れやすくなります。
さらに「グレリン」という食欲を増進させるホルモンが増加し、反対に満腹感を伝える「レプチン」が減少。
このホルモンバランスの乱れにより食べすぎを招き、結果として血糖値スパイクを引き起こしやすくなります。
こうした悪循環を断ち切るには、毎日7〜8時間程度の十分な睡眠を確保することが基本です。あわせて、寝具の見直しや室温・照明の調整など、睡眠環境を整えることも効果的。
たとえば、血流をサポートする設計が施されたリカバリーウェア「BAKUNE(バクネ)」を活用すれば、就寝時の疲労回復を助け、快適な睡眠空間を後押ししてくれます。
関連記事:リカバリーウェアの効果や選び方を詳しく解説した記事はこちら
- BAKUNE Dry Men's
- 株式会社TENTIAL
今すぐできる食後の眠気対策


湯浅 道子
まずは簡単にできる眠気対策から始めてみましょう!
午後の仕事や家事を乗り切るには、眠気に振り回されたくないですよね。
ここでは、特別な準備なしで今すぐ試せる午後の眠気対策を紹介します。
対策できそうなものから、ぜひ試してみましょう。
眠気覚ましに効果的な飲み物を飲む
食後に強い眠気を感じるときは、飲み物でリフレッシュするのが効果的です。
なかでも代表的なのがコーヒー。ブラックコーヒーに含まれるカフェインは覚醒作用があるうえ、コーヒーの香りが脳を刺激し、目を覚ますきっかけになります。
コーヒー以外にも、玉露のようにカフェイン含有量が多い緑茶や紅茶も選択肢のひとつです。
また、ミントティーのように清涼感のある香りのハーブティーや、刺激のある炭酸水なども、気分を切り替えたいときにおすすめです。
ガムを噛む
手軽にできる眠気対策として、ガムを噛むのは効果的な方法のひとつです。
実際に、ガムを噛むことで眠気が低下し、脳の前頭前野の活動が高まる傾向が確認されています※1。
咀嚼にはリズムがあるため、覚醒効果だけでなく、リラックスやストレス軽減にもつながるとされており、集中力を高めたいときや気分を切り替えたい場面にも役立ちます。
特にミント系のガムは清涼感があり、リフレッシュにもぴったり。
ただし、糖分を多く含むガムは血糖値の急上昇を招く可能性があるため、シュガーレスタイプを選ぶのがおすすめです。
また、あご関節に不安がある方は噛みすぎに注意しましょう。
※1:川野常夫ほか「NIRSを用いたガム咀嚼による眠気抑制の定量的評価」『人間工学』第56巻 Supplement号、2020年
ストレッチや散歩などの運動をする
食後に眠気を感じたときは、ストレッチや散歩などの軽い運動をするのもおすすめです。
首や肩を回したり、軽く屈伸したりするだけでも血流が促され、体が目覚めやすくなります。
筋肉が動くことで全身の巡りが良くなり、眠気の解消だけでなく集中力の回復にもつながります。
さらに、ストレッチには副交感神経を整える作用があり、気分を落ち着かせるリラックス効果も期待できます。
長時間座って作業している人は、1〜2時間に一度を目安に、簡単なストレッチを行うと血行不良の予防にもなります。
立ち上がって腕を伸ばす、肩を大きく回すといった動きでも十分です。
ストレッチを行う際は、無理のない範囲で呼吸を止めずにゆっくり行いましょう。
痛みを感じたらすぐに中断し、心地よく伸ばすことを意識してください。
深呼吸をする
深呼吸は、自律神経のバランスを整えて、リラックス効果が期待できるシンプルかつ効果的な方法です。
呼吸をゆっくり整えることで、血行が促進され、脳へ酸素が行き渡りやすくなるため、眠気をやわらげることにつながります。
特に、緊張やストレスが原因で眠気を感じやすくなっている場合には、深呼吸によって副交感神経が優位になり、心身ともに落ち着きやすくなります。
眠気を感じたら、まずは背筋を伸ばし、肩の力を抜いて静かに座りましょう。
目を閉じて呼吸に意識を向けながら、鼻から大きく吸って、口からゆっくり吐き出す。
これを数回繰り返すだけでも気分がリフレッシュされ、集中力が戻ってくるのを実感できるはずです。
明日以降の食後の眠気を「食事」から改善する方法


湯浅 道子
食事の順番や内容を変えることで、食後の眠気を軽減できることもあります。
食後の眠気は、食事の食べ方や食材の選び方によって軽減できることがあります。
特別な食材や調理法を用意しなくても、今日から意識できる工夫を紹介します。
食物繊維が豊富な野菜から食べる
食事の際は、まず食物繊維を多く含む野菜から食べはじめるのがおすすめです。
サラダや温野菜、海藻類、きのこ類などを最初に摂る習慣をつけましょう。
いわゆる「ベジファースト」を意識することで、食物繊維が糖質の吸収をゆるやかにし、血糖値の急上昇を防ぐ働きが期待できます。
血糖値の変動が安定すれば、食後の眠気の軽減にもつながります。
次にたんぱく質をとる
野菜を食べたあとは、鶏肉や焼き魚、豆腐、納豆、卵料理などのたんぱく質を意識して摂るようにしましょう。
野菜に続いてたんぱく質を摂ることで、消化に時間がかかり満腹感が長く続きやすくなります。
その結果、炭水化物の食べすぎを防ぎ、血糖値の上昇もさらにゆるやかになります。
- ザバスプロテイン100 リッチショコラ味
- 株式会社明治
炭水化物は最後にとる
白米やパン、パスタなどの炭水化物は、なるべく食事の最後にとるようにしましょう。糖質を後回しにすることで、血糖値の急上昇を防ぎ、インスリンの過剰な分泌を抑えることができます。
基本は「野菜 → たんぱく質 → 炭水化物」の順。この順番を意識するだけでも、血糖値スパイクのリスクを軽減し、食後の眠気やだるさの予防につながります。
関連記事:無性に食べたくなる原因を知って罪悪感ゼロを目指そう!おすすめの食べ物を紹介
低GI食品を取り入れる
食後の眠気を防ぐには「GI値」を意識した食材選びも効果的です。
GI値とは、食品を摂取したあとの血糖値の上がりやすさを示す指標で、高いほど血糖値が急激に上昇しやすくなります。
血糖値の急上昇は、その後の急降下を引き起こし、いわゆる“血糖値スパイク”によって眠気やだるさがあらわれやすくなります。
そのため、GI値が低い食品を選ぶことで、血糖値の変動を抑え、眠気を軽減しやすくなるのです。
たとえば、主食なら白米より玄米、食パンより全粒粉パン、うどんよりそばがおすすめです。果物を選ぶ際も、バナナよりリンゴや梨といったGI値の低いものがよいでしょう。
「どれが低GI食品なのかわからない」と感じるかもしれませんが、まずはよく食べる主食や間食のGI値をチェックしてみましょう。
一度覚えてしまえば、日々の食品選びがぐっとラクになります。
GI値の低い食品を習慣的に取り入れることは、眠気対策だけでなく、血糖値コントロールや生活習慣病の予防にもつながります。
無理のない範囲で、少しずつ置き換えていくことから始めてみましょう。
食べすぎずに「腹八分目」を心がける
食後の眠気を防ぐには、食べすぎを避けることが大切です。「腹八分目」を意識するだけで、血糖値の急上昇や消化器官への負担を軽減できます。
過剰に食べると、消化に多くの血流が集中し、脳への血流が減って眠気を感じやすくなります。
さらに、体重増加や生活習慣病のリスクも高まるため、日頃から食事の量をコントロールしましょう。
ついつい食べすぎてしまう人は「よく噛んでゆっくり食べる」ことを習慣にすると満腹感を得やすくなります。
また、テレビやスマホを見ながらの“ながら食べ”を避け、食事に集中しましょう。
ゆっくりよく噛んで食べる
よく噛んで食べることは、眠気対策としても有効です。咀嚼によって唾液の分泌が促され、消化酵素の働きが活発になります。
その結果、胃腸の負担が軽くなり、消化のために血流が過剰に集中するのを防ぎやすくできるのが魅力です。
また、噛むことで脳内の満腹中枢が刺激されるため、食べすぎを防げます。
結果的に血糖値の急上昇も抑えられ、食後の眠気を感じにくくなるというわけです。
目安としては、一口あたり20回以上噛むのが理想的。
さらに「ながら食べ」を避け、スマホやテレビを見ずに食事に集中することで、自然と噛む回数も増え、満足感も得やすくなります。
甘いお菓子や清涼飲料水は極力さける
甘いお菓子や清涼飲料水は、血糖値を急激に上昇させたあと急降下させるため、強い眠気を引き起こしやすくなります。
これは、過剰に分泌されたインスリンが血糖値を急激に下げ、その反動でエネルギー不足を招くためです。
一時的に満腹感を得られることもありますが、糖質中心で栄養バランスに欠けるため、疲労感が残りやすくなります。
また、カフェイン入りの清涼飲料は覚醒作用がありますが、効果が長続きせず、かえって眠気がぶり返すこともあります。
さらに、糖分の過剰摂取は腸内環境を乱し、消化機能に負担をかけて眠気を強める要因になる可能性も。
間食には低糖質でビタミンやたんぱく質などの栄養素をバランスよく含む食品を選び、甘い飲食物はできるだけ避けましょう。
関連記事:【我慢の限界】太らないお菓子10選!コンビニで買えるダイエットおやつを紹介
- be LEGEND(ビーレジェンド)プロテイン
- 株式会社RealStyle
明日以降の食後の眠気を「生活習慣から」から改善する方法


湯浅 道子
生活習慣を見直すことで、食後の眠気をやわらげることも可能です。
食事内容だけでなく、日々の生活習慣を意識することも、食後の眠気対策につながります。
ここでは、手軽に取り入れやすい3つの習慣を紹介します。
カフェインを適度に摂取する
カフェインには覚醒作用があり、眠気を軽減する効果が期待できます。
コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれており、集中力を高める働きもあるため、日常的にうまく摂取したい成分です。
朝の目覚めや昼食後など、眠気が気になるタイミングで摂取すると効果的でしょう。
ただし、カフェインの効き方には個人差があるため、体調や感覚に合わせて量やタイミングを調整することが重要です。
また、過剰に摂ると睡眠の質が低下したり、依存につながるリスクもあります。一般的には1日あたりカフェイン200〜300mg程度が適量とされています。
また、夕方以降にカフェインを摂ると、就寝時の眠気を妨げることがあるため、就寝予定の数時間前からは控えるようにしましょう。
あわせて、水やお茶と一緒に飲んで脱水を防ぐことも忘れないようにしてください。
BCAAサプリを取り入れる
食後の眠気対策として、BCAAサプリメントを取り入れるのも一つの方法です。BCAAは代謝や筋肉の回復に関与するアミノ酸で、疲労感の軽減に役立つとされています。
炭水化物を摂取すると、脳内で「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌が活発になります。
セロトニンにはリラックス作用がある一方で眠気を誘発。
さらに体内では睡眠ホルモンのメラトニンにも変換されるため、食後に眠くなる要因の一つです。
ここで注目すべきは、BCAAとセロトニンの原料であるトリプトファンの関係です。
BCAAもトリプトファンも、どちらも脳内に入る際に同じ輸送経路を使います。
そのため、BCAAの血中濃度が高いとトリプトファンの侵入が抑えられ、結果としてセロトニンによる眠気の軽減が期待できるのです。
午後の強い眠気や疲労感に悩まされている方は、BCAAサプリの摂取を試してみましょう。
睡眠時間を確保する
質の良い睡眠は、食後の眠気を抑えるうえで欠かせません。
睡眠が不足すると自律神経のバランスが乱れ、血糖値のコントロールがうまくいかなくなります。
さらに、睡眠不足によって食欲を高めるホルモン「グレリン」が増え、満腹感をもたらす「レプチン」が減少し、食べすぎの原因にも。
結果として、血糖値の乱高下や眠気につながりやすくなります。
一般的に理想とされる睡眠時間は7~8時間。毎日できるだけ同じ時間に就寝・起床する習慣を意識しましょう。
また、睡眠の質を高めるには環境づくりも重要です。
たとえば、睡眠時にリカバリーウェアを活用することで、疲労回復できリラックスしやすくなるという声もあります。
気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:リカバリーウェアの効果や選び方を解説した記事はこちら
- BAKUNE Dry Men's
- 株式会社TENTIAL
今日から始めよう!食後の眠気対策を習慣に

食後の眠気には、血糖値スパイクや消化の負担、疲労の蓄積など複数の要因が関係しています。
まずは、コーヒーや緑茶でのカフェイン摂取、ストレッチや深呼吸といった手軽な対策から始めてみましょう。
また、食事の順番を「野菜→たんぱく質→炭水化物」にする、よく噛んで食べるなどの工夫も有効です。
あわせて、毎日の睡眠をしっかり確保することも忘れずに。できることから少しずつ習慣化して、午後のパフォーマンス低下を防ぎましょう。
- BAKUNE Dry Men's
- 株式会社TENTIAL