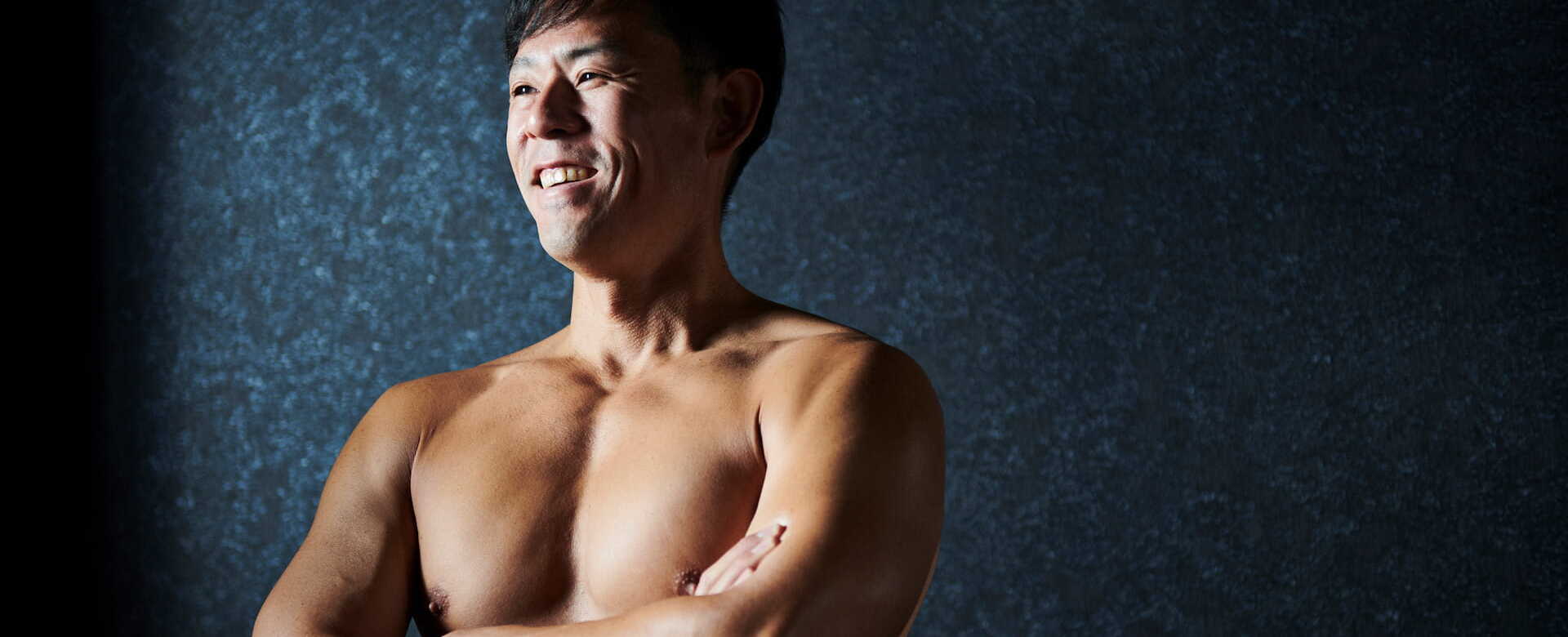肩の可動域をストレッチで広げてコリ解消!ゴルフのスイング向上にもつながる

監修者情報

正覺 友香里
ゴルフコーチ・ゴルフクラブアドバイザー
中学2年でゴルフを始め、高校で県大会優勝。ゴルフクラブアドバイザーやキャディとしての勤務経験を持ち、現在は初心者〜中級者向けにマンツーマンレッスンを行う。
元ドラコンプロで、九州のタイトルマッチ戦2位の実績あり。
■資格
USGTF(全米ゴルフ指導者連盟)ティーチングプロ
肩まわりが凝り固まる3つの理由


正覺 友香里
肩まわりが凝り固まってしまうのは「関節の可動域の低下」「正しい姿勢を保てていないこと」「肩まわりの筋肉の緊張」の3つが主な要因です。
肩まわりはおもに僧帽筋、菱形筋(りょうけいきん)、胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)など多くの筋肉が集まって連動している部分。そのため、さまざまな理由によって凝り固まってしまうのです。
まずはじめに、肩をはじめとした肩まわりの筋肉が凝り固まってしまう3つの理由について解説していきます。
関節の可動域低下
肩まわりが凝り固まる原因のひとつに、関節の可動域の低下が挙げられます。特に肩関節や肩甲骨の動きが悪くなると、周囲の筋肉が十分に使われず、次第に硬くなっていきます。加齢や運動不足によって可動域は狭まりやすく、年齢を重ねるほど影響を受けやすくなります。
しかし、日頃からストレッチや軽い運動を取り入れることで、関節の動きは維持・改善が可能です。年齢に関係なく、今からでも対策は十分にできますよ。
関連記事:股関節の柔軟性を高めるストレッチやヨガを紹介している記事はこちら
正しい姿勢を保てていない
日常的に正しい姿勢を維持できていないことも、肩まわりが凝り固まる大きな原因のひとつです。特に多くの人が悩まされている猫背や巻き肩は、肩甲骨の動きを妨げ、可動域を狭める要因となります。その結果、肩周辺の筋肉が緊張しやすくなり、慢性的なコリへとつながっていきます。
さらに、首が前方に突き出た状態であるストレートネックも、首や肩に過度な負担をかけ、筋肉のこわばりを引き起こす一因です。近年スマートフォンの長時間使用によって増えているので注意が必要です。
肩まわりの筋肉が固くなっている
関節の可動域や姿勢に加え、肩まわりの筋肉そのものが硬くなっていることも、コリや不快感を招く大きな要因です。長時間にわたるデスクワークやスマートフォン操作によって同じ姿勢が続くと、筋肉は次第に柔軟性を失い、血流も滞りがちになります。また、トレーニングによる使いすぎや、運動後のケア不足により筋肉疲労が蓄積している場合も、緊張が慢性化しやすくなります。
こうした状態を改善するためには、ストレッチや軽めの筋トレを取り入れて、肩まわりの筋肉を適度に動かし、柔軟性を高めることが重要です。
肩まわりの可動域を広げるメリット

凝り固まった肩まわりの可動域を広げることで、さまざまな効果が期待できます。ここでは、特に注目したい4つのメリットについて詳しく解説します。
- 肩・首のコリ改善や予防につながる
- ケガの予防につながる
- 正しい姿勢を保てるようになる
- スポーツのパフォーマンスが上がる
肩・首のコリ改善や予防につながる
肩まわりの可動域が広がると、肩甲骨の動きがスムーズになり、血流も改善されます。血流が促進されることで筋肉の緊張がやわらぎ、慢性的な首や肩のコリが軽減されやすくなります。
さらに、首や肩の筋肉に余計な負担がかからなくなるため、ストレートネックや巻き肩の予防にもつながります。
ケガの予防につながる
肩まわりの可動域の拡大は、関節や筋肉の柔軟性を高め、肩や腕への負担を軽減します。その結果、動作時の不自然な力みや偏った使い方を防ぐことができ、スポーツ中の捻挫や筋肉の損傷など、さまざまなケガのリスクを下げることができます。
また、加齢に伴って起こりやすい四十肩や五十肩といった症状の予防にも効果的です。
正しい姿勢を保てるようになる
肩まわりの可動域が広がると、肩甲骨が滑らかに動くようになり、本来あるべき位置に自然と収まりやすくなります。これにより、上半身の軸が整い、猫背や巻き肩などの姿勢の乱れが改善されやすくなります。姿勢が安定すると、体幹のバランスも取りやすくなり、日常動作がスムーズになるほか、見た目の印象も改善され、疲れにくい体づくりにもつながります。
スポーツのパフォーマンスが上がる
肩まわりの可動域が広がると、動作に無駄な力がかかりにくくなり、筋力やスピードを効率良く発揮できるようになります。
たとえば、ゴルフではスイングの可動域が広がることでヘッドスピードが上がり、飛距離アップが期待できます。また、テニスや野球のように肩を大きく使うスポーツでも、フォームの安定や力の伝達効率が向上し、パフォーマンス全体が底上げされます。
関連記事:ゴルフ上達に必要な筋肉とおすすめの筋トレを紹介した記事はこちら
肩まわりの可動域を広げるストレッチ【座ったままでもOK】

次に、座ったままでも手軽に行える肩まわりのストレッチを3つ紹介します。
どれも肩関節や肩甲骨の可動域を広げるのに効果的で、テレビを見ながらや寝起きのベッドの上など、日常のちょっとした時間にも取り入れやすいストレッチです。本記事を参考にぜひ実践してみてください。
肩甲骨ストレッチ
肩甲骨まわりのストレッチは、肩こりや姿勢の改善に効果的です。座ったまま行える種目も多く、デスクワークの合間や自宅で手軽に取り入れられます。肩甲骨をしっかり動かすことで、僧帽筋や菱形筋などの筋肉がほぐれ、血流促進にもつながります。
腕回し
チューブを肩幅よりやや広めに持ち、腕を大きく回すことで肩甲骨をしっかり動かすストレッチです。肩まわりの筋肉をほぐし、肩関節の柔軟性を高めるほか、肩こりの緩和にも効果的です。チューブがなくてもタオルで代用できます。
ポイント
- チューブやタオルがたるまないように、しっかり両手で引っ張る。
- 肩幅よりやや広めの手幅で行う。
- 肩甲骨がしっかり動くよう、肩から大きく回す。
- 腰が反らないように体幹を安定させ、無理のない範囲で実施する。
肩甲骨のストレッチは、毎日少しずつでも継続することで肩まわりの可動域が広がり、肩こりの予防や姿勢改善に役立ちます。詳しいやり方やほかの肩甲骨ストレッチについては、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:肩甲骨ストレッチの正しいやり方を解説した記事はこちら
背中のストレッチ
背中まわりの筋肉が硬くなると、猫背になりやすく、首や肩への負担も増えてしまいます。こまめにストレッチを行い、背中の柔軟性を保つことが大切です。
背中のストレッチは肩甲骨ストレッチと一部重なりますが、併用することでより高い効果が期待できますよ。
エアチンニング
エアチンニングは、懸垂(チンニング)のような動作で肩甲骨を動かすストレッチです。肩甲骨周辺の筋肉をアクティブに使うことで血流を促進し、肩こりや猫背の改善が期待できます。椅子に座ったまま行えるため、体力に自信がない方でも取り組みやすいエクササイズです。
ポイント
- 動作中は常に背筋を伸ばし、丸まらないよう意識する。
- 肩甲骨を寄せる感覚を持ちながら、背中の筋肉に集中する。
- 呼吸を止めず、動きに合わせて自然に吐く・吸うを繰り返す。
- 力任せに引かず、ゆっくりとコントロールした動作で行う。
背中のストレッチは、背中全体の緊張を緩め、姿勢の安定や肩こりの予防に役立ちます。詳しいやり方やほかの背中のストレッチについては、以下の記事をご覧ください。
関連記事:背中の凝りをほぐすストレッチのやり方を紹介した記事はこちら
三角筋ストレッチ
三角筋は肩の代表的な筋肉で、硬くなると首や肩まわりに張りや違和感が出やすくなります。特に巻き肩や猫背の原因にもなりやすいため、背中や肩甲骨のストレッチと合わせて行うのがおすすめです。
三角筋は前部・中部・後部の3つに分かれており、それぞれに合ったストレッチ方法があります。座ったまま行える種目も多いため、デスクワークや家事の合間などにも取り入れやすいのが特徴です。
三角筋後部のストレッチ
三角筋後部のストレッチは、座ったまま、肘を顔の高さまで持ち上げ、反対の手で胸の方に引き寄せるだけの簡単なストレッチです。
ポイント
- 肘を引き寄せる際は、反対方向に体を軽くひねるとストレッチ効果が高まる。
- 背中側から肩にかけて、筋肉全体が動いている感覚を意識する。
- 肩や首に力が入らないよう、リラックスした状態で行う。
三角筋後部をしっかり動かすことで、肩まわり全体の可動域が広がり、肩こりや巻き肩の予防にもつながります。詳しいやり方については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:三角筋ストレッチの正しいやり方を解説した記事はこちら
- NÜOBELL(ヌオベル)32kg
- 株式会社コンプライアンス
肩まわりのストレッチに関するよくある質問
1日何分ストレッチするべき?
1回あたりのストレッチは5〜10分程度を目安に、1日2〜3回行うのが理想的です。起床後・お昼休憩・お風呂上がりなど、体が温まっているタイミングに実施すると、筋肉が伸びやすく、継続もしやすくなります。
また、1種目につき30秒前後はポーズをキープするのがおすすめです。はじめのうちは関節や筋肉が硬く、伸ばすのがつらく感じるかもしれませんが「痛気持ちいい」と感じる程度を目安に、無理のない範囲で続けてみましょう。
ストレッチを続けても肩こりが解消しないのはなぜ?
筋肉のコリが強くなりすぎている場合、ストレッチだけでは十分に改善できないこともあります。血行不良が原因の場合は、マッサージや蒸しタオル、入浴などで温めながらほぐす方法を併用するのが効果的です。
また、猫背や巻き肩といった姿勢の崩れが根本的な原因になっている場合、ストレッチだけでなく姿勢改善を目的としたエクササイズも取り入れる必要があります。ご自身の体の状態に合わせながら、ストレッチと組み合わせて対策していくことが大切です。
肩まわりの可動域を広げて日常生活を快適に!

この記事では、肩まわりが凝り固まる主な原因から、可動域を広げるメリット、そして自宅で実践しやすいストレッチまで紹介しました。
肩まわりは日常の姿勢や習慣によって硬くなりやすい部位ですが、少しの意識と継続的なケアで柔軟性を保つことができます。肩こりの予防はもちろん、姿勢の改善やケガの防止、スポーツ時のパフォーマンス向上にもつながりますよ。ぜひ本記事を参考に、今日から肩まわりのケアを習慣にしてみてください。